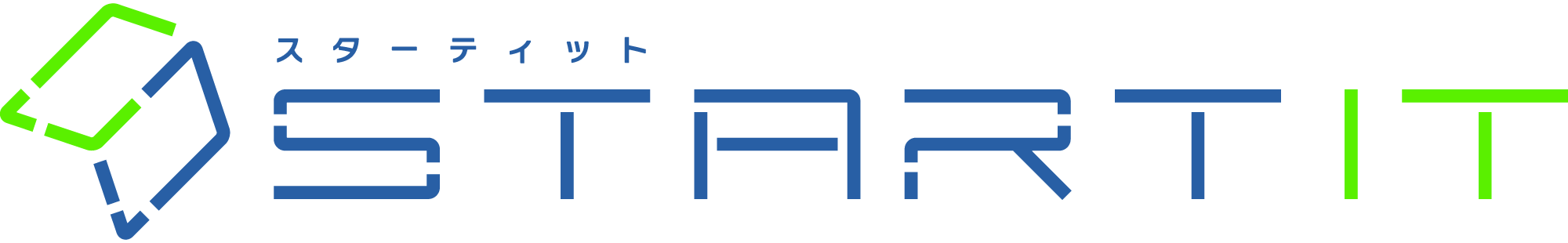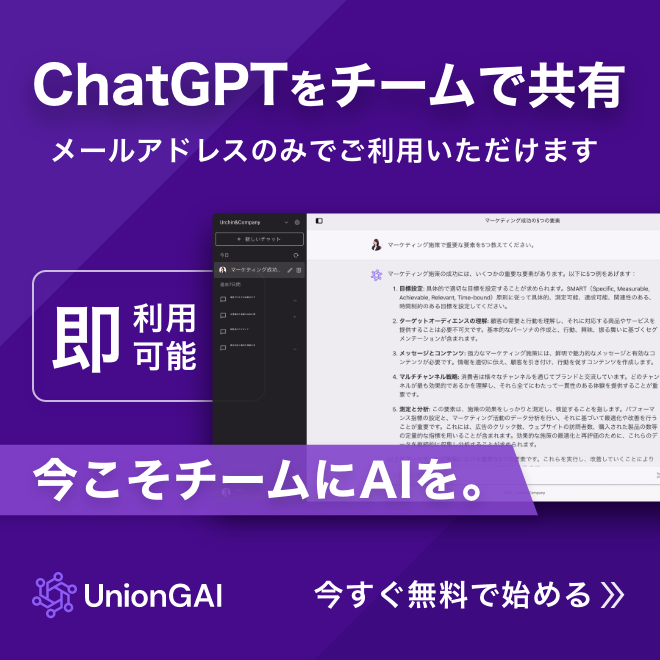営業利益が落ちる原因はどこにある?見直したいポイントや成功事例を解説
自社の売上が上がるのは純粋に喜ばしいことです。売上が上がればビジネスを継続できますし周囲からの評価も上がり、事業を拡大させるための予算もアップさせることができるでしょう。
しかし、場合によっては「売上は上がっているものの利益が出ない」というケースもあります。売上と利益のどちらを重視すべきかは判断が分かれる場合もありますが、一般的には利益の向上を目指して事業を展開するのがよいと言われているのではないでしょうか。
この記事では、営業利益が落ちる原因やその解決方法について事例付きで解説します。自社の事業をよくよく精査し、骨太な収益体制を構築しましょう。
売上が上がっているのに利益が出ない原因

売上が上がっているのに利益が出ない原因は、一体どこにあるのでしょうか。まずは営業効率が落ちる原因について紐解いていきましょう。
リソースの配分が悪い
営業利益が落ちる原因として1つ目に挙げられるのは、リソースの配分が悪いというものです。企業が使えるリソースには限りがあるため、それをどこにどのように配分するかによって業績や利益率は大きく変わってきます。
売上が上がっているのに利益が出ていない場合、リソースを効率良く活用できていない可能性があります。そうなると、「売上は上がっているけどコストも大きくなる」という状態になり、結果的に利益率が下がるわけです。
この場合はリソースの配分を適切に行えば営業利益は改善されますが、そのためには現場や業務内容をしっかりと精査する必要があるでしょう。
原価率が高い
純粋に原価率が高い場合も、利益率が下がります。99円で仕入れたものを100円で売るより、90円で仕入れたものを100円で売った方が利益率が高いという話です。
ただ、業種や商品種別によって原価率はある程度一定に保たれているため、原価率が高いせいで利益が出ていない場合は改善が難しいかもしれません。業種を変えたり、より安い仕入れ値をつけてくれる業者を探す必要があります。
あるいは、商品価格を上げることも利益改善手法の一つです。しかし、値段を上げるというのはイコール商品品質やサービス品質の増加も期待されることになるため、場合によっては難しいところでしょう。
その他コストが高い
ビジネスを行うにあたってはコストがつきものですが、それらが高騰化した場合も営業利益が落ちる原因になります。一例としては、「人件費」「オフィス代」「備品代」といったものが挙げられるでしょう。
コストを完全にゼロにするのは難しいですが、不要なところにかける必要はありません。「現在どこにどのようなコストが発生しているか」「それぞれの費用対効果は適切か」などの視点を持って精査すれば売上を維持したままコストを削減することができ、利益率の向上に繋がります。
営業利益を上げるために取り組みたいこと
次に、営業利益を上げるために取り組みたいことをお伝えします。この辺りは業種や会社が置かれている立場によって大きく異なるところなので、自社に合った手法を模索することも大切です。
生産性や費用対効果の向上
生産性や費用対効果を向上させることができれば、営業利益アップに繋がります。生産性も費用対効果も「費やしたリソース(コスト)からどの程度の成果が得られたか」といった指標になるため、高くなればなるほど効率の良い事業形態が構築されていることになります。
では、一体どのようにして生産性や費用対効果を上げればよいのでしょうか。方法はいくつかありますが、まずは自社の業務を洗い出し、それぞれの生産性や費用対効果を精査するところから始めましょう。
実態を知ることが、業務改善への第一歩です。
新規取引先の開拓
優良な新規取引先を開拓することができれば、営業効率のアップが期待できます。顧客の特性も色々なので、中には「営業工数がかかる割には発注数が低いところ」もあれば「ルーチンで毎年大きな発注をしてくれるところ」もあるのではないでしょうか。
後者のような取引先ばかりであればよいのですが、なかなかそうもいきません。しかし、そこで諦めるのではなく絶えず新規取引先を開拓することが重要です。
費用対効果の高い顧客を見つけることができれば、営業利益率が落ちる原因を排除し、向上が見込めます。また、新規開拓活動を行うことにより、「自社は市場からどのような目で見られているのか」といった情報を得ることもできるでしょう。
システムの活用
システムを上手く活用すれば、営業利益率をアップさせることが可能です。何故システムの活用が営業利益率のアップに繋がるかというと、システムを導入することで既存の業務をシステムが代替することにより、余ったリソースをより効率の良い部門に回せるからです。
例えば、営業部員の経費精算をシステム活用で効率化したとしましょう。そうなると営業マンの時間が空くことになり、その分既存顧客を訪問したり新規開拓する余地が生まれます。
それが、事業全体にとってプラスに働くことは言うまでもないでしょう。
システムを導入・活用するメリット

システムを導入・活用するメリットとしては下記のようなものが挙げられます。
業務効率化に繋がる
システムを適切に活用することで、業務効率化が可能です。システムにより従来作業を自動化する、ワークフローを可視化し効率化するなどの手法が考えられるでしょう。
業務効率化を達成することで労働生産性が向上し、同一リソースからより多くの成果を得ることができるようになります。すなわち、費用(リソース)対効果が高まるわけです。
それにより、同じ人員や体制での売上向上が狙えます。単純作業はシステムにより自動化し、人の手をより重要な業務に割けるからです。
知識やノウハウが社内に積み上がる
システムを活用することで、業務知識やノウハウを個人でなく社内に積み上げることが可能です。従来、業務の遂行を担当者がブラックボックス的に委ねていたことも多かったのではないでしょうか。
そのやり方にもメリットはありますが、業務知識やノウハウが個人に蓄積されるという難点があります。それらが個人に集約されてしまうことで「特定の個人が不在だと業務が回らない」といった不具合が生じることもあるでしょう。
業務の属人性を100%排除するのは難しいですが、システムの活用により緩和できます。それ以外にも知識が社内に積み上がることにより「教育コストの低下」「事業の再現性強化」といったメリットも考えられます。
利益率が上がる
システムを活用することで、利益率の向上にも繋がるでしょう。利益は大まかに「売上ーコスト」で求められるため、売上を上げるかコストを下げれば利益は大きくなります。
システムが売上をアップさせるケース(要因)として、下記のようなものが挙げられます。
- 顧客との関係を管理しニーズに適切に応える
- 営業フローを可視化し成功率の高いモデルを構築する
- マーケティングフローを半自動化し販促効率を上げる
それぞれ活用すべきシステムは異なりますが、システムによるデータの収集および活用がポイントです。
また、業務効率化を達成できれば、売上から得られる利益も大きくなるでしょう。コスト削減により、さまざまな費用を軽減できるからです。
業務システムの一例
では次に、業務システムの一例をご紹介します。多種多様な中から、自社が求める成果を発揮してくれるものを選びましょう。
CRM
CRMはCustomer Relationship Managementの略であり、日本語だと「顧客管理システム」と呼ばれています。CRMはさまざまな面から顧客を把握し、細やかなニーズへの対応から売上を最大化させるためのシステムです。
CRMには、主に下記のような機能が搭載されています。
- 顧客情報管理
- 分析およびマーケティング
- プロモーション管理
- メール配信
顧客にまつわる情報を記録し、そこからニーズの分析を行い適切なマーケティングやプロモーションを行います。
SFA
SFAはSales Force Automationの略であり、日本語だと「営業支援システム」と呼ばれています。SFAを導入することで営業活動をさまざまに支援することができ、営業フローや成約率の向上を目指せるでしょう。
SFAには。下記のような機能が搭載されています。
- 顧客管理
- 案件管理
- 行動管理
- 予実管理
SFAでもCRMと同様、顧客にまつわるさまざまなデータをシステムに記録可能です。加えて、顧客に対し今何を行っているかが一目で分かる案件管理、営業パーソンの行動や結果を確認できる行動管理機能なども搭載されています。
システム活用で利益率を向上させた事例

続いて、システムを活用して利益率を向上させた事例をご紹介します。
遠隔デモンストレーションによる営業活動:エムオーテックス
エムオーテックスは、IT資産管理ツールの開発および販売を手掛けている会社です。同社では、販売代理店から見込み客を紹介してもらった後に直接訪問して製品のデモンストレーションを行うという販売形態をとっていました。
しかし、遠隔地まで訪問するコストの増大や電話で操作方法を伝えるなどのコミュニケーションが難しいという問題を抱えていました。それを解決するためにシステムを整えオンライン上の営業に切り替え、遠隔地からのデモンストレーションを可能にし、コスト削減に成功しました。
スマホを利用し業務効率化:大塚倉庫株式会社
大塚倉庫株式会社は、大塚製薬の製品管理などを行っている会社です。同社ではドライバーの長時間労働が問題になっており、それを改善するためにシステムを導入しました。
具体的には独自のスマホアプリを開発し、積み込みや荷降ろしの負担軽減や伝票処理の効率化などが挙げられます。結果としてトラックドライバーの滞在時間を大きく減少させることができ、業務効率化に繋がりました。
経費精算システムを活用し作業時間の時短:ドーム
ドームは、さまざまなスポーツ用品やサプリメントの開発および販売を手掛けている会社です。同社では、領収の管理や会計システムとの連携に問題を抱えていました。
そこで経費精算システムを導入し作業の効率化を図ったところ、業務時間の大幅な削減に成功しました。
AIを活用した営業活動の可能性

それでは、最後にAIを活用した営業活動の可能性についてご紹介します。
AIチャットボットによる問い合わせ対応の効率化
営業活動においてAIチャットボットを導入することは、問い合わせ対応のスピードと正確性を向上させる方法の一つです。
特に、顧客からの問い合わせが急増する際に活用できます。
チャットボットは24時間稼働し、基本的なFAQに迅速な回答を提供します。
これにより、営業チームは重要なタスクに集中でき、顧客からの待ち時間を大幅に減らすことができます。
チャットボットの訓練にはChatGPTのようなモデルを活用し、カスタマイズして導入することで、迅速で適切な応答を実現できるでしょう。
AIによる顧客ニーズの予測
AIを使った顧客ニーズの予測は、営業戦略を最適化するための貴重な手段です。
ChatGPTを利用して顧客データを分析し、顧客の行動パターンや購買履歴を把握しましょう。
これにより、顧客の嗜好やニーズを理解し、ターゲットに合った提案やセールスアプローチを展開できます。
たとえば、特定の製品に興味を持つ顧客に関連商品の情報を提供したり、セグメントごとに適切なメッセージを送ったりすることができます。これにより、顧客満足度の向上と売上の増加が期待できます。
AIによる営業プロセスの自動化
AIを利用して営業プロセスを自動化することで、チームの生産性を向上させましょう。
ChatGPTをチーム内で共有し、ルーチン業務や繰り返しのタスクを効率化します。
具体的には、見積もりや契約書の生成、データ入力などをAIに任せることで、営業担当者はより重要なクライアントとの関係構築や戦略的なタスクに集中できます。
この自動化により、ヒューマンエラーを減らし、スピーディなプロセスを実現します。
AIを駆使した営業プロセスの自動化は、効率向上とチームの負担軽減につながります。
まとめ
営業利益が落ちる原因を一概に確定することはできませんが、一つずつつぶさに精査すれば要因が少しずつ見えてくるのではないでしょうか。営業利益が上がらない場合、まずは各業務を分析し、生産性や費用対効果を調べることが重要です。
その上で効率の悪い業務から効率の良い業務へとリソースを移動させることができれば、利益率のアップが見込めるでしょう。そのためにシステムを活用するのも一つの手ですので、積極的に検討することをおすすめします。
自社に適したシステムを導入し、営業利益の向上に努めましょう。